
大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。
うろたえず、媚びない。
そんなジャズにこだわる放浪派へ。
主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。
大橋 郁
松井三思呂
吉田輝之
平田憲彦
![]()
撰者:大橋 郁

【Amazon のCD情報】
第46回と第50回で、松井さんがNYのジャズ・クラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」について、その歴史を紹介しつつ、そこで記録された名盤を紹介しておられた。【リンク】
そこで今回の私は、その手法を真似させて頂いて、デンマークの首都コペンハーゲンにあるジャズ・クラブ「カフェ・モンマルトル」(Jazzhus Montmartre)を軸に、ここで実況録音された愛聴盤のいくつかを紹介したい。
※
バド・パウエルやケニー・ドリューなど、欧州へ移住する米国ジャズメンのことは既に何度か取り上げた。彼らの多くは、アメリカでの黒人の扱いの低さに比べて、芸術家の扱いをしてくれるヨーロッパの生活に波調があった。コペンハーゲンに移住したミュージシャンは他にも大勢いるが、彼らの多くはコペンハーゲンにおいては、カフェ・モンマルトルをホームグラウンドとして活動した。このため、カフェ・モンマルトルで収録されたアルバムは実に多い。実は第61回で取り上げた「バド・パウエル/バウンシング・ウィズ・バド」もこの店で録音されている。
※
さて、ニューヨークのヴィレッジ・ヴァンガードは1935年開店だが、カフェ・モンマルトルはこれに24年遅れて、1959年にデンマークの首都コペンハーゲンの中心部にオープンした。1961年からは、新しいオーナーであるカンプ・ラーセンと共に新しい場所に移るが、この頃レギュラー・ハウス・トリオとなったのがケニー・ドリュー (p), アレックス・リール (dr)、ニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセンである。1976年にはオーナーがケイ・ソレンセンに代わり、さらに別の場所に移転して、カフェ・モンマルトルは、ヨーロッパ随一のジャズ・クラブとして名声を馳せ、ヨーロッパの「ヴィレッジ・ヴァンガード」と呼ばれる。
しかし1989年のケイ・ソレンセンの死後、新しいオーナーによってクラブはテクノ音楽に走るなど方向性を見誤り、1995年には閉店してしまった。 しかし、2010年5月にはルネ・バックによって1961年当時の場所でジャズ・カフェとして復活して現在に至っている。
カフェ・モンマルトルを通して、欧州のミュージシャンと米国のミュージシャン(欧州ツアー中または、移住組かに関わらず)は、影響を受けたり、与えたりしてきた。さて、そんなカフェ・モンマルトルでの記録の中から、4枚のアルバムを選んだ。早速、紹介していきたい。

スタン・ゲッツ&ケニー・バロン
ピープル・タイム
Stan Getz & Kenny Barron
People Time
【Amazon のCD情報】
1958年〜1961年の3年間、スタン・ゲッツは家族と一緒にデンマーク、コペンハーゲンに住んだ。このアルバムはそれよりもずっと後の1991年の録音であり、ケニーバロン(p)との二人だけのデュオ。
本当に流麗なテナー・サックスとピアノだ。特にケニー・バロンのピアノは、音に色がついているような美しいピアノである。まるで品の良いおしゃべりの上手な女性に語りかけられているようだ。そして、これ以上ないくらいにスタン・ゲッツのテナー・サックスを支え、引立たせ、よくサポートしている。出るところと引っ込むところをよく識ったピアニストだと思う。
私は、ケニー・バロンのピアノ・トリオのアルバムを何枚か所有しているが、ケニー・バロンのプレーの中で最も好きなプレーはと聞かれれば、このアルバムを挙げるだろう。当たり前であるが、ドラムやベースが入ったコンボと違って、ソロやデュオの際には、細かい音まで聞き分けられてしまうので演奏する側にとっては、ごまかしがきかない。ここでの二人は、全ての音の隅々まで行き届いた細やかさのある演奏だ。
スタン・ゲッツという人は、若い頃から麻薬欲しさにピストル強盗をして逮捕されたこともあるくらい、麻薬やアルコールで苦労した人らしい。私生活は決して誉められたものではなかったようだが、ここでの演奏はそんなことは全く感じさせない。むしろ、心の中は澄み渡って落ち着いた状態で吹いているようだ。
またこのアルバムは、1991年6月にスタンッゲッツが肝臓癌で亡くなる3か月前に録音されたものだが、癌の痛みに耐えながらの演奏であったらしい。ケニー・バロンはその苦しむ様を目の当たりにして見ていた。このケニー・バロンのこの配慮に満ちた濃密なピアノは、ゲッツへの敬慕と愛情の表われではないだろうか。
現在2枚組のCDとして発売されているが、7枚組のコンプリートセットも発売されている。7枚組を買っても良いかなと思わせてくれる極上の内容であり、自分がカフェ・モンマルトルの聴衆のひとりになったかのような錯覚さえ起こさせてくれる。

ジャッキー・マクリーン
ライブ・アット・モンマルトル
Jackie McLean
Live At Montmartre
【Amazon のCD情報】
コペンハーゲンで、ニールス・ウィンターが1972年に立ち上げたジャズ・レーベル「スティープル・チェイス・レコード」は、良質のレコードを世に出し続け、欧州でもきってのジャズ・レーベルに成長する。(参考:第85回ケニー・ドリュー)
デンマークにおけるスティープル・チェイス・レコードとカフェ・モンマルトルの関係は、もしかしたらNYにおけるヴィレッジ・ヴァンガードとブルー・ノートやプレスティッジ・レコードとの関係に似ているかも知れないなどと、勝手に想像している。同じ町におけるジャズの普及やミュージシャンの育成をそれぞれの立場から支援していたのではないか。
さて、そのスティープル・チェイス・レーベルの記念すべき第一弾が、「ジャッキー・マクリーン・ライブ・アット・モンマルトル」だ。1972年に録音されている。
ジャッキー・マクリーン(as)は、1967年にブルーノートに吹き込んだ「デーモンズ・ダンス」以降、録音から遠ざかって大学で黒人文化について教鞭をとっており、5年間の沈黙を破っての復帰作だった。中身は、ケニー・ドリュー・トリオをバックにしたストレートなワン・ホーンで、オーソドックスなハードバップ。肩の力の抜けた気負いのないリラックスした雰囲気だ。キチンと準備をしたとは思われない、ラフで荒削りな演奏である。しかし、一聴してマクリーンとわかる音色もマクリーン節も健在である。観客の歓声も臨場感あふれている。
A面の1曲目はチャップリンの名画「モダンタイムス」の挿入歌「スマイル」。
ケニー・ドーハム(tp)のアルバム「マタドール」で、同じ曲をマクリーン自身が共演している。ここでは、当時と同様にアップテンポのバップスタイルで熱く吹く。テーマが終わったところで、「ド・ソソラソ・シ・ド」のいわゆる「コントのオチ」まで挿入してコミカルなソロが始まる。
この曲は元々バラードで、チャップリンの映画ではあの感動的なラストシーンで使われていた。家も仕事も失い警察に追われ、絶望の淵にいる孤児の娘が "What's the use of trying?" (頑張ってもどうにもならないのね)といって泣き出した時、チャップリンが娘を励まし、口の端を上げて「ほら、笑って!」という仕草を見せる。そして二人で足取り軽く一本道を歩いてゆくシーンで映画は終わる。一方、歌詞の中には、"What's the use of crying?" (泣いてどうなるんだ?笑いさえすれば、人生は捨てたもんじゃない。)という韻を踏んだフレーズを含む。希望に満ち溢れた歌であり、マクリーンの復活とスティープル・チェイスの門出に相応しい曲だ。
A面2曲目(Das Dat)は松井さんが第2回の当コラムで推挙したブルーノートにおけるマクリーンの名作「It's Time」にも収録されている、ベットリとした濃厚なブルース。聴き比べると、やはりスティープル・チェイス盤は終盤部分でベースがずれたり、アレックス・リール(dr)が終了部分を間違えたりして、聴衆の笑い声が入っている等、ジャムセッション的な粗さが目立つが、オーソドックスなバップスタイルで豪快に吹く姿は変わらないし、むしろソロ内容そのものは伸び伸びとしていて、正に「楽しいバップ」といった雰囲気が伝わってくる。
B面1曲目のパーカーズムードと2曲目のコンファメーションはともにパーカー・ナンバーのバップ・チューン。パーカー曲を取り上げていることは、マクリーンがヨーロッパにおける初録音で、原点回帰しようとしている姿勢を表しているのではないか。

ダラー・ブランド
アフリカン・ピアノ
Dollar Brand
African Piano
【Amazon のCD情報】
ダラー・ブランドは、南アフリカのケープタウン出身のピアニスト。62年頃からは国外に出て、主にヨーロッパで生活していたようだが、このアルバムは1969年にソロピアノで吹き込まれた。この時既に海外生活が長くなっており、一層故国である南アフリカを強く意識するようになっていたのかも知れない。アメリカに生まれて育った通常のジャズメンと違っているのはブルースを通過していないということであろう。しかし、使うコードの響きやリズム感など、ゴスペルとの類似性を随所に感じる。
1969年当時といえば、南アフリカは、アパルトヘイト時代である。ケープタウンやヨハネスブルグなどは、ニューヨークとは比較にならないくらい犯罪発生率が高く、白人による黒人利益の搾取・剥奪は合法的であり、米国ジャズメン以下の社会的状況であったのだろう。11分もある1曲目の「ブラ・ジョー・フロム・キリマンジャロ」のシンプルに延々と続く重たい左手は、アフリカの大地に根差しているようにも聞こえるし、苦悩に満ちているようにも感じる。このアルバムの雰囲気を決定づける印象的な曲だ。白眉は何と言っても3曲目の「ムーン」。こちらは一転して明るい曲調で、強力な左手に乗せて右手は縦横無尽、変幻自在に走り回る。
曲リストでは8曲入っているが、それぞれの曲は切れ目なく演奏されており、組曲のようである。全体を通して聴けば40分程度あるが、いっときも飽きることなく聞かせてくれる。シンプルなタイトルそのままに、アフリカ的なるものを強く感じさせるアルバムである。永年の愛聴盤であり、本当に素晴らしいアルバムだと思う。
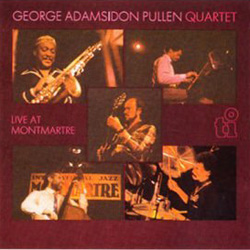
ジョージ・アダムス〜ドン・プーレン・カルテット
ライブ・アット・カフェ・モンマルトル
George Adams / Don Pullen
Live At Montmartre
【Amazon のCD情報】
ジョージ・アダムス〜ドン・プーレン・カルテットは、これまでにもこのコラムで何度か登場している。松井さんも第50回のヴィレッジ・ヴァンガードでのライブ特集の一環として取り上げておられる。このアルバムは1985年4月の録音であり、この黄金のカルテットの最盛期の真っただ中である。このグループのライブは、いつも一切手抜きのない白熱の演奏なのだが、この日はジョン・スコフィールド(g)がゲストとして加わっていることが良い刺激になったのか、ジョージも、プーレンも切れまくっている。
ここでのジョン・スコフィールド(g)は、音色こそフュージョンぽいチューニングをしているが、内容的には全くカルテットの邪魔にならない加わり方をしている。逆に全体のサウンドが引き締まったようである。録音技術の高さのせいか、ピアノやベースの音も非常に聞きとりやすい。ジョン・スコフィールドは殆どの曲において、コードプレーをせず、ジョージ・アダムスと一緒に、テーマをユニゾンで弾いている。これにより音が分厚くなり、実に気持ち良いのだ。ぶっつけのジャムセッションとは違って、よくリサーサルを重ねた演奏会だったようだ。
全5曲乗りまくりで、捨て曲なしなのだが、敢えてのお薦めはA面1曲目「I.J.」の超高速大迫力アドリブ。そして3曲目のユーモラスなテーマの「ウェル・アイ・ゲス・ウィ・ネヴァー・ノウ」。B面2曲目の11分に及ぶ傑作バラード「ソング・エヴァーラスティング」である。A-3、B-2はドン・プーレン作。プーレン(p)は、もの凄いピアノを弾く人だが、実にいい曲を書く人でもある。もちろん、あの右手の「打拳奏法」も健在である。
※
ヨーロッパには沢山の国があるが、欧州全体が米国一国程度の広さなので、移動にもさほど時間がかからない。その上、米国と違って時差もないので欧州域内の方が、米国内での東岸〜西岸よりも距離感は短いかも知れない。そんな中「カフェ・モンマルトル」は、コペンハーゲン在住者のみならずヨーロッパ中のジャズメンに愛され、中心的な役割を果たしてきた。パリでもロンドンでもなく、北欧の小国に生まれた奇跡の店で繰り広げられたライブの一端をこのようにして聞くことが出来るのを、嬉しく思う。
![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
