
大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。
うろたえず、媚びない。
そんなジャズにこだわる放浪派へ。
主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。
大橋 郁
松井三思呂
吉田輝之
平田憲彦
![]()
バド・パウエル
撰者:吉田輝之
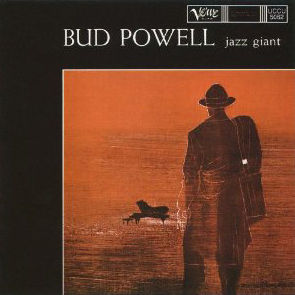
【Amazon のディスク情報】
こんにちは、猛暑のなか家に帰るとクーラーが故障してオロオロしてしまった吉田輝之です。歳をとるとダメですね。子供の頃はクーラーがなくても熱帯夜なんてヘッチャラだったのに。
さて今週の一枚はとりあえず「Jazz Giant/Bud Powell」ですが、すいません、先に言っときますが、話にあまりまとまりがありません。パウエルにまつわる断章として読んで下さい。
※
【その1 バドのおじいさんって何者?】
3年程前、ネットのWikipedia(日本語版)でバド・パウエルの項目を読んでいて、目が点になってしまった。
『1924年、ニューヨークに生まれる。パウエルの祖父はフラメンコ・ギタリストで、父はストライド・ピアニスト、兄のウィリアムはトランペット奏者という音楽一家で育つ。』
祖父が「フラメンコ・ギタリスト」?・・・??・・???・
パウエルの父が1890年頃の生まれといわれているので、祖父は1860〜1870年頃の生まれだろうか。はっきり言って、この時代、(というか現代でもそうなのかもしれないが)アメリカ黒人がフラメンコ・ギタリストになるなんて有り得るだろうか。
フラメンコまたはそれに近いスペイン音楽・舞踊が世界的に認識されたのは思いのほか早い。フラメンコ界において20世紀最大のギタリストのサビーカスそして同じく最大の踊り手のカルメン・アマーヤがスペインの内乱を逃れ、アメリカに移住したのが1936年、彼らは南米から北米を回りフラメンコを広く知らしめた。ビリー・ホリディがフラメンコ史上最高の歌手と言われるニーニャ・デー・ロス・ぺイネスを讃えた「DEEP SONG」を録音したのが1947年だ。
ちなみに日本には昭和4年(1929年)に、スペイン舞踏団(ラ・アルヘンティーナ)が来日していることからみて、フラメンコを含むスペイン音楽舞踊団はかなり早い時期から世界的に演奏活動をしていたようだ。
さらに草の根の部分でもフラメンコの主体たるジプシーは旧大陸全土だけではなく、新大陸にも開拓時代から南部を中心に移り住み、現在でも100万人程のジプシーがアメリカに住むという。
そう考えれば、19世紀のアメリカ黒人がフラメンコという音楽を知っていた可能性は100%否定することはできない。しかし、ジプシーという閉鎖的な共同体によるギター・歌・踊りが三位一体でなされる音楽を、レコードもない当時、やはり閉鎖的な黒人社会の一人が演奏していたというのはどうしても想像の域を超えている。
パウエルの祖父についてかなり調べたが、詳しく書かれた資料は見つからなかった。只、15年程前に買ったバド・パウエルの「Jazz Giant」の輸入盤CDのライナーノーツ(Gary Giddins)で次の短い文書を見つけ、今度は黒目がなくなる程驚いてしまった。
「His grandfather had pick up Flamenco guitar in Cuba during the Spanish American War」
「pick up Flamenco guitar」というのはフラメンコという「音楽」を演奏していたというより、普通のクラシックギターより少し小ぶりのフラメンコギターという「楽器」を演奏していたという意味ではないのか。
しかし何より驚いたのはその後に続く「米西戦争の間キューバで」フラメンコギターを弾いていたことである。米西戦争とは1898年、ハバナ湾でアメリカ戦艦がスペイン軍に撃沈されて始まり、結果アメリカがスペインからキューバ、プエルトリコ、フィリピン、グァム島を奪い取った戦争だ。特にキューバでは同年7月1日、アメリカ陸軍兵士約17,000人がサン・ファンヒルでスペイン軍14,000人を一日で破り勝利した。その時の義勇騎兵隊ラフ・ライダースを率いて英雄となったのがセオドア・ルーズベルトだ。
そしてこの米陸軍兵隊には「バファロー・ソルジャー」も参戦していた。「バファロー・ソルジャー」と言えば、ボブ・マーレーが「戦う黒人」の象徴として唄った同曲名が思い浮かぶが、もともとは南北戦争時にアメリカ議会で認められた正規の「黒人だけによる」部隊または黒人兵の通称で、勇気あるそして激烈な戦いぶりで多くの功績をあげたことで知られる。
驚いたことに、このキューバでの戦いにおけるバファロー・ソルジャーにはチャールズ・ミンガスとデクスター・ゴードンの祖父も参戦しているのだ。
パウエル、ミンガス、ゴードンの3人は言うまでもなく、1940年代に、共にバップ革命を推進した仲間だが、後年パウエルはミンガスとは「JAZZ AT MASSEY HALL(1953年)」で、ゴードンとは「OUR MAN IN PARIS(1963年)」で歴史的名盤を残している仲だ。
先の短い文章だけでは、バド・パウエルの祖父が軍楽隊に参加したのかコンバット(戦闘隊)に参加したのか、さらには軍隊に参加してキューバに行ったのかわからない。しかし、この3人の祖父が偶然とはいえ、ともに米西戦争時にキューバにいたというのは何か運命の綾を感じさせるではないか。
話しを少し戻そう。もし1898年の夏にキューバの歓楽街に繰り出したとしたら、そこでフラメンコそのものではないが、極めてフラメンコ〜スペイン音楽と深い関係にある音楽を耳にしただろう。
それは「ハバネラ」だ。
ハバネラは1791年のハイチ革命が起き、その避難民によりキューバにもたらされたフランス系のコントルダンスが源流だ。コントルダンスにスペインのリズム形式と黒人のリズム感覚が加わりハバネラが形成された。ハバネラは船乗り達によってスペインに伝わり19世紀の末には「スペイン舞曲」となる。その時代に生まれたのがビゼーの歌劇「カルメン」(1875年)中でカルメンが唄う『ハバネラ(恋は野の歌)』であり、またスペインのイラディエルが1860年に作曲し現在でもラテン音楽のスタンダードである『ラ・パロマ』だ。
ハバネラは庶民から貴族まで全ての階層で好まれイギリスやフランスのサロンでも栄華を極めたという。さらにハバネラはフラメンコと混ざり合いブエノスアイレスのボタでタンゴのルーツとなる。
アメリカでも1935年にコール・ポーターが「BIGIN THE BEGUINE(ビギン・ザ・ビギン」を作曲し(ビギンはマルチニック島の舞曲だが、この曲での実際のリズムはハバネラだ)、アーチー・ショー楽団が大ヒットを飛ばした。
ハバネラは19世紀から20世紀にかけ旧大陸から新大陸に亘って全ての階層、人種、民族を虜にした史上初の世界音楽だった。
僕の想像では、パウエルの祖父がキューバで演奏した、もしくは会得したのはフラメンコというより「ハバネラ」ではなかったのかと、僕は想像していた。しかし確証はもてない。
この文章を読んで祖父がフラメンコ(?)を演奏していたこととバド・パウエルの音楽とどう関係があるのかと疑問に思われる方もいるだろう。また、殆どのジャズファンはこのことに奇異に思うことも興味をもつこともないだろう。
これは10代の頃からBLACK MUSIC FUNDAMENTALIST(黒人音楽原理主義者)であるとともにHISPANOFILO(スペイン狂)であった僕のごく私的な興味だ。
彼のルーツに関係あるかどうかはわからないが、バド・パウエルの「ラテン趣味」には何か独特の文学的とも言える凝ったところがある。
彼の代表作でスペイン語のタイトル付けられた「UN POCO LOCO」は「ちょっとお馬鹿さん」と訳されることもあるが、LOCOというのはFOOLやSTUPIDではなくINSANEに近く「ちょっと正気じゃない」もしくは「ちょっと凄いじゃん」というニュアンスのはずだ。実際、パウエルの演奏自体「ちょっと正気じゃない」のだ。
また「Jazz Giant」一曲目の、あのそら恐ろしいまでのスピード感で演奏される「TEMPUS FUGIT」は「光陰矢のごとし」の意味のラテン語だが、アメリカでもかなり知られた慣用句らしい。しかし、もともとオリジナル盤(NORGRAN—VERVE)では「TEMPUS FUGUE−IT」と表記されており昔からその表記が妙に気になっていた。最近ネットで「上級英語への道」という英語・外来語と音楽を中心にしたブログを拝見したところ、パウエルのこの曲は「FUGUE(フーガ、遁走曲)」に引っかけたものだとの見解を読み目鱗であった。そうか、この曲はバッハだったのか。
【その2 バドは私の英雄】
秋吉敏子さんがバド・パウエルから強い影響を受けたことは有名だ。しかし彼女が講師を担当した「NHK人間講座(2004年6-7月放送)私のジャズ物語」をまとめた本を読むと、影響を受けたというレベルではなく、彼女はパウエルのことを「私の英雄」と呼ぶ。
彼女はパウエルの演奏についてこう評している。
「彼のタッチは奇麗なというのではなく、ごっつい、丸っこいタッチで、アップテンポの即興演奏は豪快そのもの、またパンクチュエイションの感覚はパウエル特有なものがありました。バラードの演奏には男性のロマンともろさが感じられ、私は彼の演奏のトリコとなりました。」
これほど見事にパウエルの演奏の本質を的確に示した評を僕は他に知らない。特に、「男性のロマンと“もろさ”が感じられ」なんて絶対に男性からは出てこない指摘だ。そう、秋吉さんの言う通り、パウエルのような天才でも私のような凡才でも男って自分では気づいていないだけで、すごく“もろい”んですよ。
そして、この文章を読んだ時、秋吉さんにとって、豪快そのものというアップテンポの即興演奏と男性特有のロマンともろさが感じられるバラード演奏の代表は共に「Jazz Giant」に収められている「TEMPUS FUGUE-IT」と「I'LL KEEP LOVING YOU」ではないかと僕は直観した。
1956年1月、秋吉さんはバークリー音楽院に入学するために渡米しボストンに到着した日、偶然にも有名なジャズクラブ「ストーリーヴィル」でパウエルの演奏を聴く。秋吉さんは、その時の演奏について「昔の凄みは感じられなかったが、内容の深さは依然としてあり、忘れられない強烈な印象を受けた」という。パウエルの演奏の後、秋吉さんはパウエルに紹介され、秋吉さんもピアノを弾くことをすすめられた。その時に、彼女は時差で体調は悪かったが「チユニジアの夜」を弾くと、その演奏を聴きパウエルは大笑いしたという。
パウエルは秋吉さんの演奏を聴き稚拙だとバカにして笑ったのではない。秋吉さんは東洋の小国から来た女性が自分とそっくりに弾くのを聞いて驚いて笑ったのだろうと書いているがそれだけではないと思う。パウエルは感動して笑ったのだ。ヒトは何か説明のつかないような恐怖とか感動を感じた時には笑うものだ。僕自身1977年に初めて山下洋輔トリオを生で見て聴いたときに感動しながら大笑いした経験がありそうとしか思えないのだ。事実その後、バド・パウエルは機会があれば秋吉さんの演奏を聴きにきたという。
ソニー・クラークやトミー・フラナガン、ハンプトン・ホーズなどバド・パウエルに強く影響を受けたピアニスト達の特に初期の演奏を聴くとその演奏は当然のごとくパウエルに似ている。だが彼らを聴いた後、バド・パウエルを聞くと、何故か、いや当たり前なのかもしれないが、パウエルの演奏は彼らの演奏と全然似ていない。
しかし、秋吉さんの演奏を聴いた後にバド・パウエルを聴くとパウエルの演奏は秋吉さんの演奏に似ているのだ。彼女自身、パウエルの影響を抜け自分のオリジナルのスタイルを確立するのに実に苦労したようだが、これはスタイルだけの問題ではなく本質の問題だと思う。
秋吉さんはパウエルの難曲中の難曲といわれる「GLASS ENCLOSURE」を聴いた時にパウエルの脳の中まで見えたという。
秋吉さんのピアニストとしての評価及び好みについては様々だ。しかし、僕は彼女の弾くUN POCO LOCOを聴いた時、その「正気のなさ」に圧倒されてしまった。秋吉さんという人はおそらく唯一、バド・パウエルがみたものと同じものをみて演奏できるピアニストだろう。
【その3 パウエルって、わからへん】
1970年代、AMラジオでかかるモダンジャズというのは決まってパーカーの「ナウ・ザ・タイム」とパウエルの「クレオパトラの夢」だった。だから「クレオパトラの夢」に関しては耳タコだったが、実際に歴史的名盤といわれる「バド・パウエルの芸術」や「アメイジング・バド・パウエルシリーズ」を聴いてみても10代の僕にはサッパリわからなかった。(これはパーカーについても同じだ)
レコードの音が悪かったこともあると思う。また、当時ジャズ界の中心にいたマッコイ・タイナーやキース・ジャレット、また最初に好きになったピアニストであるオスカー・ピーターソンがピアノを鳴らしまくるとのに対して、ペダルを殆ど使わなかったというパウエルの音は何かしょぼく聞こえ馴染めなかったということもある。高校生になりジャズ喫茶に通い出し、パウエルに影響を受けたトミー・フラナガンやソニー・クラークといったハード・バッパーに親しんでも、たまにジャズ喫茶でかかるパウエルは、どこがよいのか、やはりまるで判らなかった。
当時「俺はジャズがわかっていないのではないか」と恥ずかしくて知り合いのジャズファンにはそのことを話せなかったが、彼らと話をしているうちに、彼らもはっきりは言わないものの「パーカーとパウエルは殆ど聴いていない」ことが判り妙に安心してしまった。そのうち、僕はジャズから少し距離を置いたこともあり、そのことも気にしなくなった。
15年程前に、勤めていた会社が潰れ、再就職したが数年間は殆どレコード、CDを買わなかった。資金がなかったことが最大の理由だが、時々、「禁断症状」が出てきて、100円ショップやビデオ・CDレンタル店の中古特売コーナーで100円から300円ぐらいのCDをジャンルに関係なく大量に買うことがあった。
その中で、ダイソーで買ったジャズピアノのコンピレーションが何枚かあった。もともとこういうCDは著作権など怪しいのだが、やはりその関係か、ファッツ・ウォーラやテディ・ウィルソン、アール・ハインズ、アート・テイタム、メリー・ルー・ウィリアムスといった古典派の巨匠による50年程前以前の演奏ばかりが収められていた。もちろん音は悪く、解説書なども一切なしであった。
そのCDに、パウエルの演奏する「All God's Chillun Got Rhythm(神の子はみな踊る)」があり、この演奏を聴いた時に初めて「パウエルって凄い」「パウエルってええわ」と思った。しかし、このCDで感動したのはパウエルだけでなく、実際に初めてちゃんと聴いたといえるウォーラーもハインズもウィルソンもパウエルと同じ感覚、同列で「ええわ」と思い感動していたのだ。今思い返せば、これら古典派の巨匠の演奏を聴き耳が馴れることでパウエルが理解できるようになったのだと思う。
前述したことを重なるが、パウエルという人は彼が影響を与えた人よりも、はるかにテイタムやウィルソンといった人に近いのではないか。つまり、パウエルはモダンジャズピアノの「最初の革新者」ではなく、実はトラディショナルジャズの「最後の巨匠」ではないだろうか。パウエルが似ていると反語的に述べた秋吉さんも元々はテディ・ウィルソンを範とした人だ。おそらく僕の考えはおかしいのだろうが、パウエルを聴けば聴くほどそう思えて仕方がないのだ。
【その4 私は踊る神しか信じない】
この「神の子はみな踊る(All God's Chillun Got Rhythm)」はマルクス兄弟の映画「マルクス一番乗り(A Day at the Races)」での主題歌(?)だ。今、この映画のDVDは500円で買えるので是非見てほしいが、映画の最後、笛を吹く男につられ黒人たち歌い踊りまくるシーンで、エリントン楽団最高の女性歌手といわれたアイヴィー・アンダーソンが、この曲を歌う。
最初の部分だけ意訳してみた。
〜引用〜
神の子たちはみなリズムを得て踊る
神の子たちみなスウィングする
お前たちには金はないかもしれない、靴もないかもしれない、
神の子たちはみな憂鬱を振り払うためリズムを得て踊るんだ
All God's Chillun Got Rhythm, all God's chillun got swing
Maybe haven't got money, maybe haven't got shoes
All God's Chillun Got Rhythm for to push away their blues
〜引用以上〜
「got rhythm 」を「踊ると」訳したのは意訳だろう。歌詞的には「haven't got money」「 maybe haven't got shoes」と対比されているので「リズムを得た」と直訳した方がよいのだろうが、この曲の本質からすれば、この曲を最初に「神の子はみな踊る」と訳した人は非常に感覚的がすぐれていると思う。僕はくどくなるが合せて「リズムを得て踊る」と訳してみた。
この曲の作者は作詞はガス・カーン(Gus Kahn)、作曲はブロウニスロウ・ケイパー(BronislauKape)と、ウォルター・ジュアマン(Walter Jurmann)。3人ともユダヤ人だ。マルクス兄弟もユダヤ人だし、制作したMGMも当然ユダヤ資本だ。この場面が黒人達によって歌い踊られていることを考えれば、この曲はユダヤ人と黒人による「芸能賛歌」とも言える。
しかし、この曲が、もともと、黒人霊歌の「All God's Chillun Got Shoes」を基に作られたことを考えればそれは表面的なもので本質的に違う意味がある。
元歌の「All God's Chillun Got Shoes」はいくつかのヴァージョンがあるようだが、だいたい次のような歌詞だ。
〜引用〜
僕は靴を手に入れた 君も靴を手にいれた
神の子はみな靴を手に入れた
僕は天国に行くときに靴を履いているんだ
神様の天国を歩き回るんだ。
I got shoes you got shoes all of God's childrens got shoes
When I get to heaven gonna put on my shoes
I'm gonna walk all over God's heaven (heaven) heaven (heaven)
Everybody talkin' bout heaven ain't a goin' there heaven (heaven) heaven (heaven)
〜引用以上〜
元歌は、現生では靴も履けないほど貧しかったが、天国に行って初めて靴を履くことができたという内容だ。
「神の子はみな踊る」ではこの元歌の意を反転させて、現生では“金はないかもしれない、靴もないかもしれない”が、お前たち神の子は生きている今でも(神から与えられた)リズムがあるではないか。リズムがあれば悩みなんてヘッチャラさ、と言っているのだ。
つまり「神の子はみな踊る」という曲は来世(天国)ではなく現世で、貧しくてもリズムを得て踊ることにより魂の解放と救済されることを高らかに謳った曲なのだ。
だからこそ、この曲を差別を受けてきたジューン・クリスティーやジュディー・ガーランド、スタン・ケントン楽団やアーチー・ショーといった多くのユダヤ人系とアート・テイタム(パウエル以前にこの曲はテイタムのオハコ)やマイルスやクリフォード・ブラウンといった多くの黒人達が唄い演奏してきたのだ。
僕は今回、パウエルの演奏を何回も聴き直しているうちに、30年以上前に習ったある哲学者の言葉を唐突に思い出した。その考えはナチスがホロコーストを正当化するために政治的に曲解して引用されたが、実は反ユダヤ主義には強い嫌悪感をいだいていた哲学書の言葉だ。
「わたしが神を信ずるなら、踊る神だけを信ずるだろう。(ニーチェ)」
※
◎今回、大橋さんに、秋吉さんのNHK講座をまとめた本をお借りし、たいへん参考になりました。ありがとうございます。
【言い訳】
今回「Jazz Giant」の内容について、殆ど断片的にしか述べておらず、すいません。けど、超名盤だから私が今さらくどくど説明しなくても・・・。
録音(マスターテープ?)が悪いですが、本当にパウエル全盛期の凄さが、これでもかと詰まったレコードです。
![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
