
大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。
うろたえず、媚びない。
そんなジャズにこだわる放浪派へ。
主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。
大橋 郁
松井三思呂
吉田輝之
平田憲彦
![]()
テナーサックス編(後編)
撰者:松井三思呂

三寒四温というのでしょうか、春が近づいてくるのは良いのですが、花粉に悩まされる時期です。
さて、放浪派コラム、記念すべき50回目を書かせていただくことになり、光栄の至りです。
大橋さんの「Boogie Woogie Piano」でスタートした本コラム『KIND OF JAZZ NIGHT』も1年以上続いてきたわけで、「思えば遠くに来たもんだ!」ではないですが、私も含めて筆者4名に「ご苦労さん!」と言ってあげたい気分です。
これからも次の節目100回目指して、がんばっていきますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。
今回は前回に引き続き企画モノ、『Village Vanguard Live Collection』(テナーサックス編)の後篇をお送りします。前回は野球で言えば、先発でソニー・ロリンズ、中継ぎジョン・コルトレーンと繋いできました。今回はセットアッパーとしてアルバート・アイラー、締めのクローザーはジョージ・アダムスにお願いすることにします。
※※
アルバート・アイラーは18回と22回のコラムで、彼のラストレコーディングを採り上げているので、通算3回目の登板である。また、ここでアイラー先生を書いているわけだが、最初に結論めいたことを言わせてもらえば、「アイラーの前にアイラーなく、アイラーの後にアイラーなし!」。
と言うのは、オーネット・コールマン、アーチー・シェップ、ファラオ・サンダースといったフリー・ジャズの巨匠には、ビ・バップ〜ハード・バップ、そしてモードといった演奏形態を踏まえたうえで、そのアンチテーゼとしてフリー・ジャズに至ったバックグラウンドを感じる。その典型例がコルトレーンかもしれないが……。
しかしながら、アイラーからはそういったバックグラウンドはあまり感じられず、聞こえてくるものは幼少期に慣れ親しんだゴスペルやスピリチュアルと、その延長線上にある彼の魂の叫びだけである。この魂の叫びがジャズ演奏という枠組みのなかでは、フリーフォームなものであるだけに、フリー・ジャズとカテゴライズされているだけではないだろうか。
そういう面では、アイラーは他のフリー・ジャズの巨匠とは違って、唯我独尊、ワン・アンド・オンリーな存在である。そこが、いまだに多くのジャズファンを惹きつけている所以かもしれない。
「Albert Ayler In Greenwich Village」
(Impulse AS 9155)
本アルバムはアイラーのインパルス・レーベル移籍第一弾として、1967年に発表されたもので、アナログではA面の2曲、「For John Coltrane」、「Change Has Come」は67年の2月26日、ヴィレッジ・シアターでの録音である。ヴィレッジ・ヴァンガードでの録音はB面の2曲、「Truth Is Marching In」、「Our Prayer」で、66年の12月18日にレコーディングされている。66年12月と言えば、コルトレーンのヴィレッジ・ヴァンガード録音から5年後、コルトレーンが亡くなる7ヶ月前ということになる。
録音はジョージ・クラビンで、彼は60年代半ばにコロンビア大学の学内FMのジャズ部門責任者として、レコーディング・エンジニアのキャリアをスタートさせている。その後、本作の頃からヴァンガードでの録音も手がけ、サド・ジョーンズ=メル・ルイス・オーケストラなどの録音を行っている。現在はロサンゼルスを本拠とするレゾナンス・レコードの代表。
話が横道にそれるが、ジャズファンに「誰か一人好きなレコーディング・エンジニアをあげて下さい」と問えば、多くの人がルディ・ヴァン・ゲルダーの名前をあげるであろう。逆に言えば、ヴァン・ゲルダーが録音した作品を聴いたことのないジャズファンは皆無だと思う。ブルーノートはもちろんのこと、プレスティッジ、リバーサイド、サヴォイ、インパルス、CTIの幾多の作品を手がけており、前回紹介したロリンズとコルトレーンのヴァンガード作品も彼の録音によるもの。既にあるのかどうか知らないが、彼のディスコグラフィーを作るとしたら、相当膨大な作業が予想される。
ルディ・ヴァン・ゲルダーは1924年ニュージャージー生まれ。本職の検眼技師のかたわら独学で録音技術を身につけ、ニュージャージー州ハッケンサックの自宅居間をスタジオとして使っていた。当時、ブルーノートやプレスティッジといったインディ・レーベルは専用のスタジオを持っていなくて、ラジオ局のスタジオなどを借用していた。
そんななかで、54年にギル・メレの紹介でヴァン・ゲルダーと知遇を得たブルーノートのアルフレッド・ライオンは彼を重用し、その後ほとんど全てのブルーノートのレコーディングはヴァン・ゲルダーが担うこととなる。録音はハッケンサックの自宅スタジオや、59年の7月からはイングルウッド・クリフス(ハッケンサックから数マイル)の専用スタジオで行われている。なお、彼の功績を讃えて、今年のグラミー賞でヴァン・ゲルダーは「協会賞」を受賞している。
ところで、私の感じるヴァン・ゲルダー録音の最大の特徴は、骨太なベースとドラムのシンバルのクリアさである。これはそれほど異論のないところであろうが、ピアノについては意見の分かれるところかもしれない。友人のクラシックファンに、作品は忘れたが、ブルーノートのピアノトリオを聴かせたところ、「ピアノの音が濁っている」と言われた。確かに70年代以降のECMに代表されるヨーロッパのレーベルは、クリアで透明感に溢れたピアノ・サウンドを記録しており、それと比較すれば……。
しかし、低音に厚みを持たせることで、ジャズの持つエネルギーを表現する技法を確立したことと、その圧倒的な仕事量から、まぎれもなく「ヴァン・ゲルダー録音」=「50〜60年代のモダンジャズ・サウンド」であって、彼はジャズ史に名を刻む偉人である。
※
話をアイラーのアルバムに戻して、サイケなジャケットは好みの分かれるところかもしれないが、私は大好き。インパルス・レーベルのアルバムはおしなべて地味で、パッとしないジャケットが多いなか、移籍第一弾としてのレーベル側の意気込みも感じられる。
インパルスへの移籍は、プロデューサーであるボブ・シールにコルトレーンがアイラーを推薦したことによる。コルトレーンとアイラーはお互いを認め合い、尊敬しあう間柄であったことは紛れもない事実であり、インパルス移籍の口利きに対する感謝の気持ちもあってか、アイラーはアルバムのアタマから「コルトレーン讃歌」。
アイラーは「For John Coltrane」では、テナーではなくアルトサックスを演奏している。編成はベース×2、チェロ、バイオリンという弦楽器主体のクインテット。アイラーのアルトはそれなりに唄っている。ただ、楽器編成のせいもあるのだろうか、祝祭的なイメージは少なく、内省的な印象。
2曲目の「Change Has Come」では、アイラーはテナーサックスに持ち替え、弦楽器4人に弟のドナルド・アイラーのトランペットとビーバー・ハリスのドラムスが加わる。ここでは、ドナルド・アイラーの提示するテーマにかぶさるアイラー先生のソロが凄まじい。ナット・ヘントフは原盤ライナーで、この曲に関してダウンビート誌によるアイラーへのインタビューを引用している。「若い頃のルイ・アームストロングが演奏していたような歓びと美しさに溢れた音楽を再生したい。」
やはり、このアルバムの白眉はB面の2曲、「Truth Is Marching In」、「Our Prayer」。驚くべきことだが、この2曲が録音されたヴィレッジ・ヴァンガードにはコルトレーンが演奏を聴きに来ていた。前回のコラムでも触れたが、ロリンズのヴァンガード録音時にもコルトレーンは足を運んでおり、生涯を通じての研究熱心ぶりがうかがえる。
そのコルトレーンの目前で繰り広げられた「Truth Is Marching In」。アイラーの決して長くはなかった生涯での決定的な名演で、ラストレコーディングの演奏と甲乙つけがたい。第22回のコラムで、アイラーはコルトレーンの葬儀以降、この曲をラストレコーディングまで封印していたのではないかと記したが、この背景にはこの日の演奏があるのかもしれない。なお、楽器編成は「Change Has Come」からチェロが抜けたセクステット。
神々しい音楽である。歓びに満ちた音楽である。そして、優しさにあふれた音楽である。マーチのテーマは軍楽隊や、ディキシーランド、ニューオーリンズのセカンドラインを連想させる。このテーマに引き続き、「真実は行進してやってくる」に込められたパッションの爆発が、6人の全力疾走のフリー・インプロヴィゼーションで表現される。カッコいいっす!
「Our Prayer」は5分弱の演奏で、非常に濃密だ。第22回のコラムの繰り返しとなるが、1967年7月21日、ニューヨークのセント・ピータース・ルセラン教会で執り行われたコルトレーンの葬儀において、アイラーはドナルド・アイラー(tp)、リチャード・デイビス(b)、ミルフォード・グレイブス(ds)とのカルテットで追悼演奏に臨んだ。演奏された曲はメドレーで“Love Cry〜Truth Is Marching In〜Our Prayer”であったが、アイラーは悲しみのあまり二度も演奏を中断し、激しく慟哭した。
さて、本作もロリンズやコルトレーンのヴァンガード録音と同様、ご多分にもれずCDでは完全版が出ている。オリジナル・アルバムの4曲に加え、全14曲の2枚組で、「Holy Ghost」、「Spirits Rejoice」など名演揃い。このコラムをきっかけにゲットしたが、ここのところ自宅ではヘビーローテーションである。
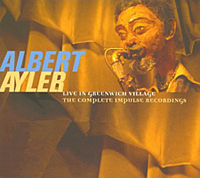
「Live In Greenwich Village〜The Complete Impulse Recordings」
(IMP 22732)
コルトレーンの葬儀から約3年半後、1970年11月25日、アイラーはニューヨークのイースト・リバーで溺死体となって発見される。24歳の軍楽隊での演奏を振り出しに、プロのジャズ・ミュージシャンとしての活動期間はたった10年間であったが、彼が与えた影響ははかり知れない。もう一度書くが、「アイラーの前にアイラーなく、アイラーの後にアイラーなし!」。
※
このあたりで、トリにバトンタッチ。クローザーはジョージ・アダムスである。紹介するアルバムは当然ながら、「Live At Village Vanguard/George Adams〜Don Pullen Quartet」(SOUL NOTE SN1094)。
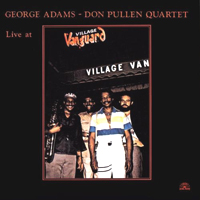
アダムス=プーレン・カルテットについては、大橋さんが第9回のコラムで既に採り上げていて、実に的確な分析をしている。それもそのはずで、そもそも私にこのバンド(彼らは「バンド」と呼びたい)を教えてくれたのは大橋さんである。86年に彼が福島に赴任した時、83年の福島でのライブ録音を聴いたことがきっかけである。
また、第9回のコラムでは、大橋さんがおいしいどころの作品はほとんど紹介しているので、是非そちらもご覧いただきたい。なお、「Live At Village Vanguard」は83年の8月19日に録音されており、前述の福島市の新聞会館でのライブとほぼ同時期の演奏ではないかと思う。
ベースのキャメロン・ブラウンを除く、ジョージ・アダムス、ドン・プーレン、ダニー・リッチモンドは、ミンガス・スクールのメンバーとして、74年のミンガスのアトランティック盤「Mingus At Carnegie Hall」(SD 1667)、「Changes One」(SD 1677)、「Changes Two」(SD 1678)で素晴らしい演奏を聴かせている。特に、カーネギーホールのライブ盤はローランド・カーク、ハミエット・ブルーイットという曲者も加わっており、大好きなアルバム。
その後、キャメロン・ブラウンを加えて、鉄板のカルテット編成となり、この4人では79年のミラノでのライブ盤「All That Funk」(Palcoscenico PAL-15002)を皮切りに、88年にダニー・リッチモンドが他界するまで数多くの名作アルバムを残す。
今回紹介するヴァンガード録音は、最も脂ののっている時期の一枚で、モダンジャズ史上屈指のライブバンドとして、実力を遺憾なく発揮した作品。4曲が収録されており、A面は「The Necessary Blues」と「Solitude」。
「The Necessary Blues」(スタジオ録音はタイムレス盤「City Gates」に収録) はサブテーマに“Thank You Very Much, Mr.Monk"とあるとおり、プーレン作のブルース曲だが、モンクの「Straight No Chaser」を想起させる。最初はごくありきたりのブルースっぽく始まるが、それで終わらないところが凄い。ピアノソロになるとプーレン節が爆発し、アダムスのテナーソロでは「Straight No Chaser」のテーマの引用や、豪放なブローにお得意のフリーキーなトーンを織り交ぜ、予想のつかない展開を見せる。それでいて、4人の一体感は失わない点に、レベルの高さを見せつける。
一転、「Solitude」はバラードである。このバンドのバラード演奏については、前のコラムで大橋さんが「抒情性と祈りのような敬虔さを感じる」と書いている。全く同感である。この曲も一聴はごくオーソドックスなバラードであるが、何度も聴き返してみると、メンバーの本気さ、真剣味に心が動かされる。
B面アタマは「Intentions」、当時しばしばライブのオープニングに演奏されていたようで、このバンドの持つ躍動感が満喫できるナンバー。アダムス、プーレンはもちろんであるが、キャメロン・ブラウンのベースとダニー・リッチモンドが素晴らしい。曲の中盤、プーレンお得意の右拳コロコロのソロから、ブラウンのベースソロに繋いでいくが、このソロが抜群のカッコ良さ。「うーん」と唸らせる職人芸。そして、アダムス、プーレンとリッチモンドの4バースで演奏は最高潮に達する。ここでのリッチモンドのプレイは「おかず」や「ひきだし」が満載で、インタープレイの迫力に圧倒される。
ジョージ・アダムス=ドン・プーレン・カルテットと名乗っているが、4人の関係は平等であったのだろう。長期間この4人で数多くのレコーディングやライブ演奏を行えたことが、それを裏付けているように思う。その面ではファラオ・サンダースを紹介したコラムでも書いたとおり、この時代に演奏スタイルは違うが、ライブバンドとしての実力で、このカルテットに肩を並べることができたのは、ウェザー・リポート、アート・アンサンブル・オブ・シカゴ、ファラオ・サンダース・カルテットぐらいではないだろうか。
アルバムの締めはミンガスに敬意を表して、彼の作曲した「Diane」。非常に美しいバラードで、アダムスとプーレンの唄心がほとばしっている。ところで、ジョージ・アダムスはサム・クックの伴奏をしていた時期があるらしく、彼がブルースなどを唄う(ヴォーカル)ことはその影響もあるのかもしれない。少し考え過ぎですかね……。
アダムスとプーレンは数多く来日しており、特にマウント・フジ・ジャズ・フェスティバルには87年から毎年出演していた。「Song From The Old Country」(プーレン作で86年のブルーノート盤「Breakthrough」に収録)はフェスのテーマ曲となり、88年には世を去ったダニー・リッチモンドに捧げるレクイエムとして、ミシェル・ヘンドリックスのヴォーカルを加えて演奏され、観客を熱狂させている(You Tubeで視聴できます!)。その後、92年にアダムスが、また95年にはプーレンが相次いでこの世を去り、現在はキャメロン・ブラウンだけが健在である。
なお、本アルバムには同日のヴァンガード録音の続編として、「Live At Village Vanguard,Vol.2」(SOUL NOTE SN1144)が出ている。中古盤屋で見かけたら買おうと思っているが、なかなか縁がなく、未だに私のウォント・リストの上位に鎮座したままである。
※※
ジョージ・アダムス=ドン・プーレン・カルテットを知るきっかけとなった福島のジャズスポット「ミンガス」には、私も一度お邪魔したことがあるが、ホームページを見ると30周年を超え、震災後も元気に営業を続けておられる。
「3.11」から1年が経過した。改めて、心から東日本大震災の犠牲者の方々のご冥福をお祈りするとともに、被災地の一日でも早い復興を願って、記念すべき50回目のコラムを閉じたい。
![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
