
大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。
うろたえず、媚びない。
そんなジャズにこだわる放浪派へ。
主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。
大橋 郁
松井三思呂
吉田輝之
平田憲彦
![]()
シダー・ウォルトン
撰者:松井三思呂
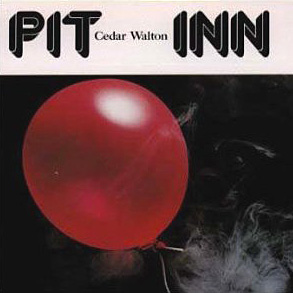
【Amazon のディスク情報】
まずはサッカー男子日本代表、ワールドカップへの出場を決めてくれました。5大会連続で、今回はブラジル開催です。おめでとうございます!
放浪派コラムも今回で90回! 100回へのカウントダウンが始まるところまで来ました。100回記念の前のキリ番を担当させていただきます。
また、100回は何か面白い企画をやりたいということで、4人で相談しています。乞うご期待!
ここのところ、私が採り上げてきたものは『ウイ・インシスト』、『銀巴里セッション』、『至上の愛』と、少し肩がこる作品が多かったので、今回はスウィング感満載で、リラックスできる作品を紹介します。
※
先日、時間潰しに書店をブラブラしていた時、ふと村上春樹氏の『意味がなければスイングはない』(文春文庫 む-5-9)が目に入った。
村上春樹氏といえば、神戸高校在学中や浪人時代、三宮のジャズ喫茶「さりげなく」や「バンビ」に通っていたことや、早稲田大学第一文学部在学中には国分寺と千駄ヶ谷でジャズ喫茶「ピーター・キャット」を経営していたことが知られている。
正確に本のタイトル名は覚えていなかったが、音楽エッセイを書いていることも知っていたので、迷いなく手に取ってみてビックリ!
というのも、最初のページから「シダー・ウォルトン〜強靭な文体を持ったマイナー・ポエト」とあり、次のページにシダー・ウォルトンのアルバム『ピット・イン』の写真、そして本文の書き出しはこうだ!
「年齢やスタイルを問わず、今現役で活躍しているジャズ・ピアニストのうちで、いちばん好きな人を一人あげてくれと言われると、まずシダー・ウォルトンの名前が頭に浮かんでくるわけだが、僕と熱烈に意見をともになさる方はたぶん(もし仮におられたとしても)かなり数少ないのではないかと推測する。」
「いやいや、私はその数少ない一人ですよ!」と心の中でつぶやきながら、ページをパラパラとめくると、11人のミュージシャンが登場している。
シダー・ウォルトンを始めとして、ジャズ・ミュージシャンではスタン・ゲッツとウィントン・マルサリス、ジャズ以外ではシューベルトからスガシカオまでと非常に幅の広い人選で、とても興味を惹かれた。
このエッセイ本を購入して、自宅に帰り、村上春樹先生の大絶賛アルバムで、私の思い出一杯アルバムでもある『ピット・イン』を久しぶりに聴こうと、レコード棚を探すものの、目的のブツがない。
悪い記憶がよみがえってきた。いつかのコラムでも書いたように、私には10数年の間、ジャズから距離を置いていた時期があって、その時に相当数のジャズLPを売り飛ばした。どうも『ピット・イン』もそのなかに入っていたようだ。
こうなると、どうしても聴きたくなった。そこで、即座にヤフオクをチェック、アナログ盤を800円という安価でゲットして、コレクションにカムバックさせたという次第。改めて、ネットオークションの便利さを実感した。
『PIT INN』
Cedar Walton
EAST WIND EW-7009
シダー・ウォルトン(p)、サム・ジョーンズ(b)、ビリー・ヒギンズ(ds)
1974年12月23日 新宿「ピット・イン」でのライヴ録音
監修:鯉沼利成、プロデューサー:伊藤八十八、守崎幸夫
録音:鈴木良博、アート・ディレクション:久保襄介
アルバム・デザイン:細川光夫、カヴァー写真:佐藤弘
※
『ピット・イン/シダー・ウォルトン』は、私が初めて買ったピアノトリオのアルバム。
いわゆるピアノトリオの「ハジレコ」で、最初に聴いたのはこのコラムでもよく登場している西宮北口のジャズ喫茶「デュオ」だと記憶しているが、三宮のジャズ喫茶「ピサ」に足繁く通っていた頃、度々リクエストしたアルバムでもある。
ここで、話が少し横道にそれるが、三宮のジャズ喫茶「ピサ」について触れたい。
「ピサ」が大のお気に入りだった訳は、まずソファーがゆったりしていて、ゆっくりできたこと。
それと、かかるレコードが私の好みのド真ん中。音量も大きからず、小さからずで、真剣にジャズと向きあうもよし、読書するもよし、ついでに居眠りするもよし(店にとっては迷惑至極!)。
ただ、今となってはこれ以外のことと言えば、店が現在の東急ハンズ南のいくたロードにあったことぐらいしか記憶がなかったところ、フェイスブックで店のマッチの画像をアップすると、当時の常連の方から貴重な情報の書き込みをいただいた。
正確な店の位置はいくたロードの岸ビル地下1階。オーディオはプリメインがサンスイのAU777。スピーカーはサンスイ製のエンクロージャーにJBLフルレンジを詰め込んだLE8T。ターンテーブルはガラード。カートリッジはシュアーのMM。というラインナップだったらしい。
つくづく、フェイスブックの持つ情報量の凄さを感じたところ。
さて、このアルバムを「デュオ」で初めて聴いた時、少し大袈裟かもしれないが、A面1曲目のシダーのオリジナル「スイート・サンデイ(SUITE SUNDAY)」に私の心は鷲掴みにされた。
心地良いサンバのリズムに乗って、無限に繰り返されるのではないかと錯覚するループ感満載のリフとともに、キャッチーなテーマが奏でられる。
明るい陽射しのなか、日曜礼拝に向かう人々のウキウキ感が伝わってくるようなイメージ。
「日曜日の組曲」と名付けられているだけあって、シダーのソロも組曲風にリズムやテンポに変化をつけ、フォービートあり、ワルツありと、全く飽きさせるところがない。
そのうえ、サイドのサム・ジョーンズ、ビリー・ヒギンズとの相性も抜群で、この曲ではビリー・ヒギンズのソロが抜群だ。このソロが終わって、テーマに戻るところの躍動感は素晴らしい。
当日、新宿「ピット・イン」に詰めかけた観客(村上春樹氏もその一人であった)も、期待を超える快演に驚いている様子が窺える。
2曲目の「コン・アルマ(CON ALMA)」、ディジー・ガレスピーのオリジナル。
レイ・ブライアントなど多くのピアニストが演奏している曲だが、シダーのトリオもラテン・リズムに乗ったミディアムテンポで、王道を進む。この王道ぶりがスゴイ、シダーのショーケースとも言うべき。
ここでも、ビリー・ヒギンズが渋く、ひねり技爆発で、砂かぶり系玄人筋を唸らせるドラミングだ。
A面ラストの「ウィズアウト・ア・ソング(WITHOUT A SONG)」で、トリオは前半のクライマックスを演出する。
演奏はゆったりとしたテンポで始まり、サム・ジョーンズの重厚なソロに引き続き、シダーが急速なテンポでソロを展開。ここらあたりから、メンバーも観客もリラックスして、掛け声も連発される。
後半のピアノとドラムスの4バースで、演奏は最高潮に達する。まさにグルーヴィーなパフォーマンス!
ここで、感心することは、ひとつには外国人ミュージシャンの来日公演にありがちな手抜きが全くないこと。
ふたつめにはライヴの場合、どこかで演奏の荒さが出てしまうところだが、そういうことは全く感じさせない。引き締まった演奏だ。
最後には、決して難しいことや、目新しいことはやっていないのに、素晴らしいダイナミズムを感じさせるところ。
約9分間のなかに、ピアノトリオのおいしいところが全て詰まっていると言えば、言い過ぎだろうか。彼らがちょっと本気になれば、これぐらいは当たり前なのだろう。
※
このあたりで、このアルバムをリリースした「EAST WIND」レーベルに触れておきたい。
「EAST WIND」は、1974年に当時日本フォノグラムの敏腕プロデューサーであった伊藤八十八氏が中心となって設立したレーベルで、5年間で約70枚のアルバムをリリースしている。
伊藤八十八氏は1946年生まれで、早稲田のニューオーリンズ・ジャズクラブに在籍。日本フォノグラムでは洋楽ポピュラー編成部に8年間所属した後、「EAST WIND」を立ち上げる。その後、彼が78年にCBS/SONYに移籍することで、「EAST WIND」レーベルは幕を閉じる。
「EAST WIND」が活動していた時期は、私が最もジャズを熱心に聴いていた時期と一致するため、今でも親近感を抱くレーベルだ。
ただ、スリー・ブラインド・マイスと比較すると、昨今の「和ジャズ」ブームのど真ん中レーベルとは言い難い。この理由は約70枚のカタログのなかで、日本人ミュージシャンのリーダー作は25枚しかなく、残りのアルバムは外国人ミュージシャン作品というラインナップにある。
特に、レーベル後期は平田さんが第12回のコラムで採り上げている「ザ・グレイト・ジャズ・トリオ」のアルバムが数多くリリースされるなど、いわゆる「和ジャズ」は数少ない。
逆に言えば、ここまで外タレのアルバムを制作できた理由は、当時の「あいミュージック」(現在の「鯉沼ミュージック」)社長の鯉沼利成氏と、その片腕であった伊藤潔氏の存在が大きかったようだ。
「鯉沼ミュージック」は70年に設立されて以来、この5月にキース・ジャレット〜ゲイリー・ピーコック〜ジャック・ディジョネットのトリオ結成30周年記念の日本公演をプロモートするなど、外国人ミュージシャンのコンサートのプロデュースとプロモートを40年以上にわたって行ってきた「呼び屋さん」である。
『ピット・イン』が録音された74年だけを見ても、当時の「あいミュージック」がプロモートした外タレのコンサートは、キース・ジャレット・カルテット、ダラー・ブランド、アン・バートン、ドン・チェリー、CTIサマー・ジャズ(ハンク・クロフォード、グローバー・ワシントン・ジュニア、ジョージ・ベンソンなど)、セシル・テイラー・ユニット、アート・アンサンブル・オブ・シカゴ、そして笠井紀美子・ウィズ・シダー・ウォルトン・トリオと多士済々だ。
そして、このなかでダラー・ブランド、アン・バートン、シダー・ウォルトン、サム・ジョーンズの4人が来日時に「EAST WIND」へリーダー作を残している。
また、初期の「EAST WIND」のアルバム・カヴァーはデザインに統一感があって、一目で「EAST WIND」と分かったものである。上部に白地の部分があって、そこにアルバム名、リーダー名、「EW」のロゴ、その下に抽象的な写真という構成。
『ピット・イン』の場合はご覧のように、風船と煙草のけむりの写真が使われている。
※
アルバムの演奏に戻ろう。
B面はシダー自作の「サントリー・ブルース(SUNTORY BLUES)」で幕を開ける。この曲はまさに「ダルマ」か「角」のロックでも飲みながら演奏しているかのようで、リラックスした雰囲気。後半のサム・ジョーンズのソロに唸らされる。
2曲目はモンクの超有名曲「ラウンド・ミッドナイト(ROUND MIDNITE)」。シダーはゆったりとしたテンポで、一音一音を丁寧に紡いでいく。
シダー・ウォルトンを「ジャズ界のショパン」と評した人がいるようだが、この曲などを聴くと、優しく柔らかいタッチの端正な演奏で、ショパンのイメージもなるほどである。ただ、村上春樹氏は「ジャズ界のショパン」には否定的で、「そのような呼称が醸し出すロマンティックな室内楽的イメージは、彼の演奏する音楽の質を偏った方向に定着させてしまうことになるのではないだろうか。」と著している。
3曲目のシダー自作「ファンタジー・イン“D”(FANTASY IN "D")」で、この夜のライヴは最高潮に達する。
この曲ではサイドの二人にはソロをまわさず、シダーが7分18秒の間、ただひたすらピアノを弾き倒す。彼は雲のように湧きあがるイマジネーションにまかせて、インプロヴィゼーションを展開していき、トリオの演奏は新宿「ピット・イン」を揺るがしていく。掛け値なしの力演だ。
大橋さんが直近のコラムで、レッド・ガーランドを「早弾きしても転ばない。そして決して崩れない。」と評しているが、シダー・ウォルトンにもあてはまるように思える。
そして、ライヴはB面ラストの「ブリーカー・ストリートのテーマ(BLEEKER ST.THEME)」で幕を閉じる。
シダーのオリジナルで、ミディアムテンポのマイナー・ブルース。グルーヴ感に満たされた観客の手拍子と掛け声のなか、メンバーが紹介される。
今回、改めてアルバムを聴いてみて、この日の演奏の凄さが蘇ってきた訳だが、現場に居合わせた村上春樹氏は、「レコードで聴く演奏の2〜3倍くらいの気迫があったように思う。」
「どんだけー!」という感じだ。
ところで、こんな演奏が残された背景には、新宿「ピット・イン」という「ハコ」の存在も大きいと思う。
驚くべきことに、このトリオは3日間連続で「ピット・イン」において、ライヴ・レコーディングを行っている。
74年12月22日は笠井紀美子の『キミコ・イズ・ヒア』、23日は本アルバム『ピット・イン』、そして24日は渡辺貞夫の『渡辺貞夫・アット・ピット・イン』。加えて、この3日間の前日の21日には、サム・ジョーンズ名義のスタジオ録音『セヴン・マインズ』を「EAST WIND」レーベルにレコーディングしている。
来日4部作、あるいは「ピット・イン」3部作という陣容だ。
※
今回のコラムでは、村上春樹氏の『意味がなければスイングはない』と絡めて、『ピット・イン/シダー・ウォルトン』の素晴らしさを紹介しました。
次回は、「ピット・イン」3部作の残り2作である『キミコ・イズ・ヒア』(トリオで歌伴)、『渡辺貞夫・アット・ピット・イン』(ワンホーン・カルテットのリズム隊)を題材に、シダー・ウォルトンと彼のトリオをもう少し掘り下げてみたいと思います。
![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
